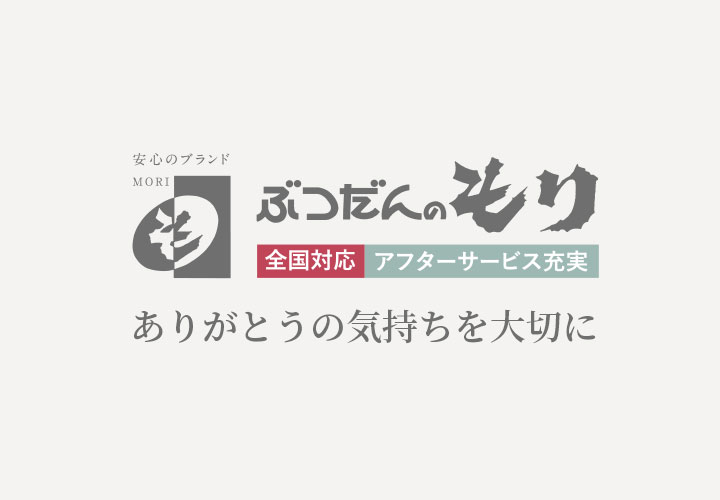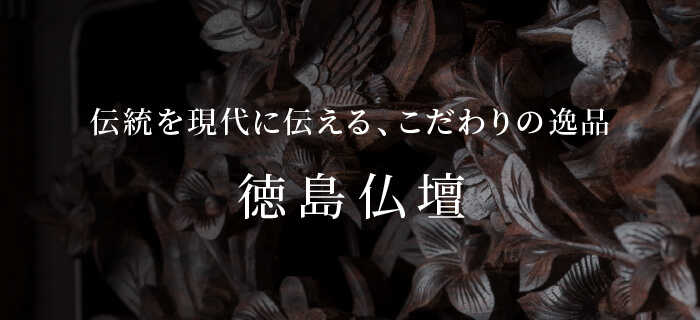浄土真宗大谷派のまつり方
お仏壇
| 宗祖 | 親鸞聖人 |
| 中興の祖 | 蓮如上人 |
| ご本尊 | 阿弥陀如来 |
歴史
承安3年(1173)、親鸞聖人は京都に生まれ9歳で得度しました。その後20年間に亘り比叡山で修行を続けますが、やがて比叡山の仏教に絶望し、法然上人を訪ねます。そこで法然上人の専修念仏の教えに帰依したのでした。 しかし、専修念仏が禁止され、越後に流罪。
その後、親鸞聖人は非僧非俗(僧に非ず俗に非ず)として「愚禿釈親鸞(ぐとくしゃくしんらん)」と名乗ります。流罪が許された後、妻子を伴って関東に移り、約20年にわたり教えを広めます。 60歳を超えた頃、京都へ帰り、90歳で亡くなるまで盛んに執筆活動を行い、同時に関東の門弟達へ手紙で教えを説きつづけました。
親鸞聖人の滅後、門弟の力により建てられた大谷廟堂(後の本願寺)は次第に衰微していきますが、八代蓮如上人によって再興をはたします。慶長7年(1602)、東本願寺は、西本願寺と分かれ、現在は親鸞聖人の教えを聞く根本道場・真宗本廟として宗門人の帰依処となっています。
お仏壇の飾りかた
御本尊・阿弥陀如来を中央に、その両脇に御脇掛(九字・十字の御名号、または親鸞聖人・蓮如上人の御影、及び側面に先祖代々の法名を奉安します。法名は掛軸にし、位牌は用いません。
※お内仏の大きさによってお荘厳が異なりますので、お手次の寺院にお訪ねください。
※これは一例です。地域や仏壇の大小などによってまつり方に違いがありますので、正しくは菩提寺にお聞きください。
参考文献:鎌倉新書「2分でわかる仏事の知識」より抜粋