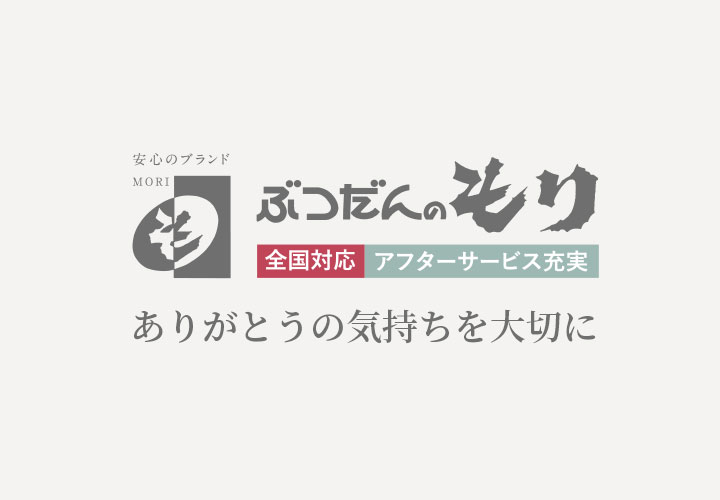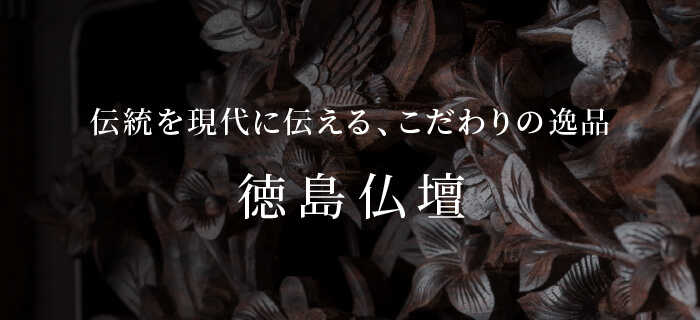日蓮宗のまつり方
お仏壇
| 宗祖 | 日蓮聖人 |
| ご本尊 | 大曼荼羅 |
歴史
日蓮は貞応元年(1222)安房国(千葉県)に生まれ、12歳で天台宗清澄寺に入り、16歳で得度します。21歳の時に比叡山へ上ると膨大な書物を読破しながら、教えを求めて園城寺、高野山などへも訪れます。こうした修行研鑽を11年続け、ついに「お釈迦さまの最高の教えである『法華経』こそが、救いのよりどころとなる唯一の教典である」という確信を得ました。
清澄寺に戻った日蓮は、建長5年(1253) 清澄山頂に登って「南無妙法蓮華経」の題目を高唱し、立教を宣言します。その後、「法華経を広めようとする行者は難にあう」という法華経自体に書かれている予言通り、「松葉谷の法難」「小松原の法難」など数々の難に遭い、死の危険にさらされることになります。
「社会に天災や疫病などが続くのは邪法・悪法がはびこっているからだ。法華経信仰によって国土の安穏をはからなければならない」と説いた『立正安国論』を執権北条時頼に提出すると、その内容を幕府に危険視され伊豆に流罪(伊豆の法難)。さらに「龍の口の法難」では斬殺寸前となりますが稲妻によって奇跡的に逃れ、佐渡に流罪となります。文永11年(1274)ようやくゆるされた日蓮は身延山に入り、61歳で生涯を閉じるまで著作と後進の育成につとめたのです。
お仏壇の飾りかた
中央には大曼荼羅か、釈迦牟尼仏、あるいは三宝尊のいずれかをご本尊としてまつります(三宝尊とは向かって右に多宝如来、中央に「南無妙法蓮華経」のお題目、左に釈迦牟尼仏を配したものです。その右に鬼子母神、左に大黒天をまつります(法華宗では逆)。そしてそれらの前中央に日蓮聖人をまつります。
※これは一例です。地域や仏壇の大小などによってまつり方に違いがありますので、正しくは菩提寺にお聞きください。
参考文献:鎌倉新書「2分でわかる仏事の知識」より抜粋